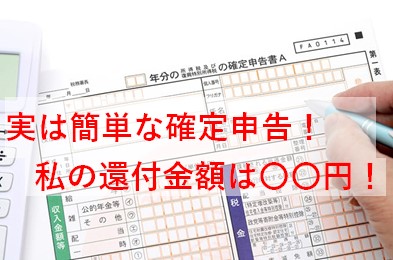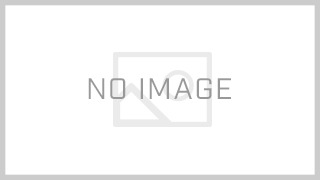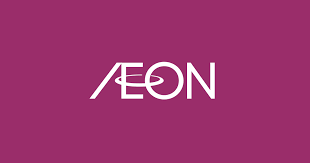こんばんは、29manです。
私はとある理由で定期的に通院しているのですが、結婚してからは妻の分も含め医療費が年間10万円を超えるようになりました。
多くの場合、医療費が10万円を超えると確定申告で医療費控除を受けることができることができるのですが、みなさんは知っていますか。
知らない方のために今日は医療費控除について記事にしたいと思います。
医療費控除とは?
医療費控除とは、病気やケガによる通院等で1年間の医療費が一定額を超えると所得から控除できるというものです。会社員の場合は税金を源泉徴収されているので、医療費控除の申告により還付金の形で支払った税金の一部が返ってきます。
この一定額というのは総所得金額により異なり、医療費控除額は以下のような式で計算されます。
〇総所得金額200万円未満の場合
医療費控除=1年間で払った医療費-保険金等で補填される金額-総所得の5%
〇総所得金額200万円以上
医療費控除=1年間で払った医療費-保険金等で補填される金額-10万円
計算式の「1年間で払った医療費」は、自分自身のものだけでなく生計を一にする家族の分を合算してもよいため、配偶者と子供の分も合算して申請することができます。
また、生計を一にしていればよいため、同居していない大学生の子供や親であっても扶養していれば合算が可能です。
総所得とは?
総所得という言葉を聞きなれない方のために簡単に説明すると、所得には給与所得だけでなく利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得など様々なものがあり、これらの所得を全て合計したものが総所得となります。
副業や配当収入の無い一般的な会社員では、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の部分が総所得に該当します。
所得の種類については機会があれば別の記事に纏めたいと思います。
保険金等で補填される金額とは?
「保険金等で補填される金額」とは、以下4項目のいずれかに該当するものを指しています。
| 1 | 生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける医療保険金や入院給付金、傷害費用保険金など |
| 2 | 社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金 例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など |
| 3 | 医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金 |
| 4 | 任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金 |
【国税庁】
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuzei/shotokukojo/iryohikojo/kokenkinhotenkin
なお、「保険金等で補填される金額」の上限は自身で支払った医療費が上限となるため、医療費5万円に対し保険の給付金が10万円であっても医療費控除の計算で差し引かれるのは5万円となります。
つまり、総所得が200万円以上である会社員Aさんの1年間の医療費が20万円だったとします。このうち骨折の治療で5万円の医療費を支払った後に8万円の保険金が下りたとすると以下のような計算になります。
医療費控除=20万円-5万円-10万円=5万円
【国税庁】
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuzei/shotokukojo/iryohikojo/iryohichokahotenkin
医療費控除の対象となるものは?
基本的に治療を目的としたものであれば医療費控除の対象となります。
美容や病気の予防は対象外ですが、治療が目的であれば病院の診療、処方薬でもドラッグストアで購入する市販薬でも保険の適用如何にかかわらず医療費控除の対象です。
イメージ的には下記のような分け方です。
| 控除対象 | 控除対象外 |
| ・病院での診療費、処方薬 ・治療を目的としたマッサージ師、鍼灸師による施術 ・通院の交通費(ガソリン代は不可) ・入院費用 ・コルセット、補聴器等の医療器具 |
・予防接種 ・治療を目的としないマッサージ |
| ・病院での処方薬 ・ドラッグストアで購入した市販の風邪薬 |
・健康の保持増進のためのサプリメント |
| ・虫歯の治療 ・入れ歯 |
・治療が目的でない歯科矯正(美容目的) |
医療費控除申請の注意点
医療費控除を受ける場合にいくつか注意点があるため記載していきます。
共働きなら総所得の多い方が申告した方が得!
最近は夫婦共働きの家庭が珍しくないと思います。我が家も共働きです。
共働きで2人とも医療費が10万円を超えている場合それぞれ確定申告してもよいのですが、医療費控除は生計を一にする家族の分を合算することができます。
所得税は累進課税方式で所得が増えるほどに税率が増えていくため、医療費控除を申請する場合は所得の多い方が纏めて申請する方が還付金が多くなります。
所得税については過去に挙げた記事を見てください。

領収書は5年間保存!
医療費控除の確定申告の方法が変更となり申請時に領収書を添付する必要が無くなりましたが、領収書は5年間の保管が義務付けられています。
申請を終えてしまったら安心しがちですが、5年間は間違っても捨てないように注意しましょう。
さいごに
1年間の医療費、領収書を見返してみると意外と掛かっているものです。
領収書を保管して年に1回確定申告するだけで還付が受けられると思えば申告しないという選択肢はありません。
確定申告という言葉だけで面倒がらずに、まずは行動に移してみましょう。